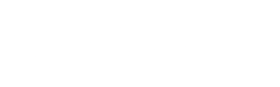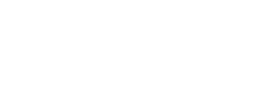関税の仕組みと計算方法について個人輸入から免税まで完全解説します
こんにちは。税理士の高荷です。
アメリカと中国の関税戦争が話題になっています。
関税とは、輸入品に課される税金です。
この関税は、輸入を生業としている事業者だけではなく、個人で海外から商品を購入する場合にも関わってきます。
そのため、関税について正しい知識を持つことは、事業者だけでなく消費者にとっても重要になります。
そこで、今回は輸入に関わる税金として、関税の仕組みと計算方法を解説します。
尚、この記事は3ページで構成されていますので、お好きな内容からご覧ください。
Page-1(このページです)
輸入品に掛かる税金
関税とは
関税の納税者
Page-2
関税の課税価格と計算方法
関税の申告・納税
Page-3
関税の税率(関税率)
少額輸入貨物に対する簡易税率
一般税率と簡易税率の判定
海外から物を輸入する場合に係る税金としては、主に次の税金が挙げられます。
関税
消費税及び地方消費税
酒税
たばこ税及びたばこ特別税
揮発油税及び地方揮発油税
石油ガス税
石油石炭税
これらのうち、3番以降は輸入品の種類に応じて課税されます。
1番の関税と2番の消費税(地方消費税)は、原則全ての輸入品に掛かります。
尚、上記7つの税金は、全て国税(地方消費税は除く)です。
今回は、このうち1番の関税について解説します。
【日本の税金は46種類、全部ご存知ですか?】
ご存知ですか?とん税【日本の税金は全部で何種類?】
関税とは、次の内容の税金です。
一部、輸出品についても課されると言われていますが、現在の日本においては「輸入品に掛かる税金=関税」と捉えてもらって問題ありません。
一口に「関税」と言っても、その範囲は非常に広大で、実は奥が深い税金でもあります。
それは、日本だけでなく輸入先の相手国(外国)が関わってくるためです。
日本国内では、関税法と関税定率法という法律を基本としています。
しかし、大きな枠組みで言うと、WTO(世界貿易機関)加盟国との共通ルールに従って関税制度を設けています。
そのため、その時々の経済・国際事情や産業の動向に合わせて、特例等が定められることになります。
アメリカや中国の関税戦争が大きく取り上げられるのは、関税が自国だけではなく他国にも影響を与える税金だからです。
この関税には、次の3つの機能があります。
国の財政機能
国内産業の保護機能
アンチ・ダンピング機能
これら3つの機能について、簡単に説明します。
関税は国が課す国税であるため、その収入は国の財源になります。
しかし、昔は国の財源として期待されていた時期もありましたが、現在は国の財源になるほどの税収はありません。
2017年度の関税収入は、約1兆円で、国の税収の2%もありません。
現在の主たる機能は、こちらになります。
海外から輸入される安価な輸入品に対して関税を課すことにより、国内産業を保護する機能です。
簡単に言うと、海外から輸入される安い牛肉をそのままの値段で売ってしまうと、国産の牛肉が売れなくなるため、輸入品に関税を掛けることで価格のバランスを取るのです。
関税が掛けられた輸入牛肉は、関税を価格で売らなければならないため、市場における価格面で国産牛肉とバランスが取れることになります。
しかし、前述したように諸外国との関係も考慮しなければならないため、一律で高い関税を掛けるというわけにはいきません。
そのため、一定の数量までは低税率(又は無税)の一次税率を採用し、一定数を超える輸入品については、比較的高い税率の二次税率を適用するなどの措置が採られることもあります。
例えば、次のような場合を考えてみます。
例)【豪州から輸入される牛肉】
豪州国内の販売価格 1,000円
豪州からの輸入(輸出)価格 800円
日本産の牛肉価格 1,000円
関税 輸入価格の15%
上記のような場合には、豪州からの輸入価格800円に関税を掛けるため、輸入牛肉の日本での価格は920円になります。
対して、日本産の牛肉は1,000円で、豪州からの輸入牛肉の方が安くなってしまいます。
本来であれば、豪州は国内販売価格の1,000円で輸出すべきところを、それよりも安い800円で輸出しています。
1,000円で輸出すれば、日本での販売価格は1,150円となり、日本産の牛肉よりも高くなります。
このように、輸出国の国内価格よりも低い価格の輸出品が、自国の産業に影響を与えることを「ダンピング」と言います。
このダンピングを是正するために、アンチ・ダンピング関税という特別な関税を掛けることがあります。
現在の関税の目的は国内産業の保護にあるため、国内産業を脅かすような輸入品に対しては、このような特別な関税を課す政策が採られるのです。
関税の納税者は、特別な規定がある場合を除いて、次の人になります。
貨物を輸入する人は、法人・個人、仕事や趣味など関係なく、物を海外から購入(輸入)する人になります。
通常は、仕入書(インボイス)の荷受人が、貨物を輸入する人にあたります。
インボイス(仕入書)とは
インボイス(Invoice)とは、納品書や請求書等の書類のことを言います。
インボイスは、発送する商品の情報が書かれた書類で、輸出側が作成する書類です。
具体的には、発送元、発送先情報といった項目や商品、数量、重量、金額(単価・総額)、取引条件などの項目が記載されています。
ようになっています。
インボイスは、輸入通関をする際に必要となります。
尚、実際の関税の取扱い上、自分で関税を計算したり、直接税関に関税を納付することは、ほぼありません。
通常は、郵便局や宅配業者、通関業者等を通じて納付することになります。
また、通関業者が通関手続きを代行する場合には、輸入者に代わって関税等の申告・立替納付を行います。
その後、輸入貨物を引渡したあとに、その費用を手数料等と一括して輸入者に請求し、輸入者が通関業者に支払う方法が一般的です。
税関(ぜいかん)と通関(つうかん)
税関とは、関税などの税金の徴収、輸出貨物・輸入貨物の通関、密輸の取締りなどを行う国の機関を言います。
税関と関税は、言葉が似ているので混同してしまいがちですが、意味するところは全く違います。
税関の一番偉い人を「税関長」と言います。
尚、日本の税関は、出入国の管理は行いません。
出入国の管理は、入国管理局という別の機関が行います。
また、通関とは貨物を輸出・輸入する際の許可を受ける手続きを言います。
具体的には、貨物の品名・種類・数量・価格などに関する事項を申告し、必要な検査を受け、関税等の税金を納付します。
通関の許可を得ないと、輸出・輸入が完了したことにはなりません。
輸入の場合には、物(貨物)を引き取ることができないことになります。
因みに、通関の許可を与えるのは、税関です。
この通関手続きは、非常に煩雑で法律等の専門的知識が必要なことから、通常は通関業者が行います。
尚、通関の許可を得ないで物を輸出入した場合には、密輸になります。